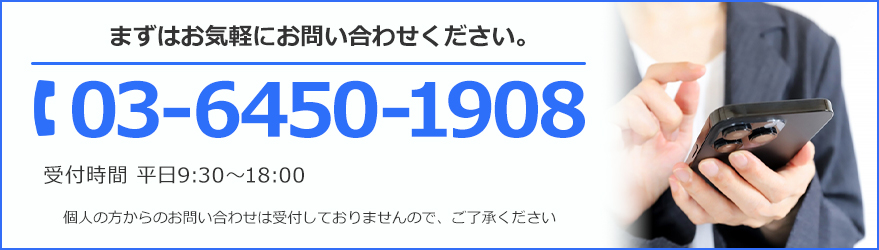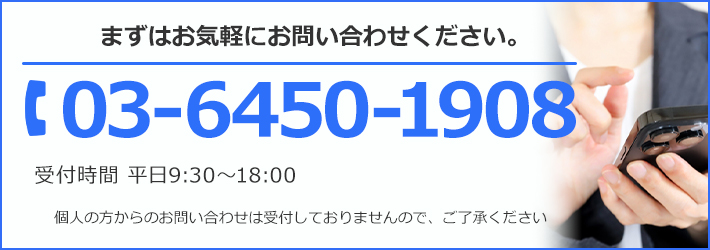システム開発契約は、契約後の仕様変更や納品後の不具合が生じやすい類型であることや、ベンダー(システム開発業務を受託する側)とユーザー(システム開発を依頼する側)の意思疎通が難しい類型であることから、トラブルが生じやすい契約といえます。
本記事では、システム開発に関する契約書の確認を頻繁に行っているベンチャー・スタートアップの法務に精通した弁護士が、システム開発でよくあるトラブルとその対応・予防策について詳しく解説します。
システム開発契約におけるよくあるトラブル
トラブル① 契約締結前に着手してしまう
契約条件が詰まっておらず契約書や発注書を作成できていないのに、納期に間に合わせる目的やユーザーが他のベンダーに依頼してしまうことを予防する目的で、ベンダーが有償の作業に着手してしまうことがあります。その後、ユーザーが他のベンダーに委託することになってしまい、契約を締結できなかったような場合、ベンダーからすれば、これまでにかかった費用をユーザーに請求したいと考えます。他方、ユーザーは、交渉を行っていただけであり契約は存在しないから支払わないと主張すると考えられます。この場合、契約書を交わしていなければ、訴訟で契約が成立していたと判断されることはかなり難しく、ベンダーが費用を回収できない可能性が高いです。
トラブル② 請負契約・準委任契約のどちらかを明確にしない
システム開発の契約は、民法の請負契約(民法632条)である場合と準委任契約(民法656条)である場合があります。この違いは、請負契約の場合、「仕事の目的物の引き渡し」と引き換えに報酬を支払うことになっている(民法633条)ため、目的物であるシステムを完成させて引き渡さなければ報酬を受け取れませんが、準委任契約は「委任事務を履行する」ことと引き換えに報酬を支払うことになっているため(民法656条、648条2項)、目的物であるシステムを完成させなくても作業分の報酬を受け取ることができます。
請負契約か準委任契約かを明確にしていないと、ベンダーは想定していた報酬を受け取れない可能性もあります。また、請負契約か委任契約かは、契約の表題だけでなく契約内容の実質面から判断されますので、契約の内容つまり条項の中身にも注意が必要です。
トラブル③ 要件定義が不十分
要件定義とは、開発工程の前段階で、開発者の視点から要求をまとめ、具体的な進め方を決めることです。要件定義が不十分なまま進んでしまうと、システムの仕様がユーザーの業務とずれてしまい、ベンダーとしては完成した後に手戻りが発生したり、ユーザーとしては報酬を減額されたり、最悪の場合システム自体が不要になってしまったりとトラブルになってしまう可能性があります。
トラブル④ 納期・支払いが遅れる
ベンダーの進捗管理が甘かったり、ユーザーが要件の追加や仕様変更を続けたりすると、システム開発がスケジュールから遅れ、納期に間に合わなくなってしまうことがあります。他方、納期に間に合ったとしても、ユーザーによる検収に時間を要したり、検収の結果手戻りや不具合があったりすると、支払いが遅れる場合もあります。
システム開発トラブルを防ぐためのポイント
相手とのコミュニケーションを十分にとる
上記のようなトラブルを防ぐには、まず何よりも、ベンダーとユーザーが十分なコミュニケーションをとることが重要です。何のためにどのようなシステムを開発するのか、そのシステムはどのように利用される予定か、契約は請負契約か準委任契約か、完成品の基準や納期、支払期限など、認識のずれがないよう綿密に打ち合わせましょう。また、打ち合わせた内容は、議事録やメールなどの形で残しておくことが必要です。
(なお余談ですが、弁護士への契約書作成業務などもこれに似ている側面があります。雇用契約書などの典型的であり、定型的な契約書は弁護士に丸投げして作成の依頼が可能ですが、システム開発契約書や業務委託契約などの場合には、中身を細かく設定するため、依頼者と綿密な打ち合わせが必要になります。)
完成物の要件定義を徹底する
十分なコミュニケーションでプロジェクト内容を明確にしたら、要件定義を徹底的に行うことも重要です。「誰がどの画面でどんな操作をするのか」を聞き出し、開発するシステムが満たすべき条件を整理して要件定義することが必要です。ユーザーはシステム開発に慣れていない場合が多いですから、要件定義をする中で、ユーザーの希望で叶えられること叶えられないことや叶える方法をベンダーの視点で整理して示すことが、トラブル防止につながります。
要件定義に基づいて契約書を作成する
要件定義ができたら、契約書を作成し取り交わしましょう。請負契約か準委任契約か、完成品の基準や納期、支払期限など、コミュニケーションして出てきた条件を契約書に盛り込むことが必要です。また、要件の追加・変更や納期の遅延など不測の事態が発生した場合の対応についても定めておく必要があります。
弁護士に契約書作成を依頼するべき理由
上述のとおり、システム開発契約はトラブルが発生しやすいため、契約書に当事者の意思をきちんと反映し、様々なトラブルも想定した内容にする必要があります。弁護士にシステム開発の契約書の作成を依頼すると、当事者の意思を明確に反映した契約書を作成することができ、未然にトラブルを防止できますし、トラブルになってしまった際に備え自社に有利な条項を入れておくこともできます。
この場合、先ほど述べた通り、依頼者と弁護士が協議を重ね、依頼者の意向に沿った契約書を作成していくことになります。
システム開発契約をご検討の方はぜひご相談ください
当事務所では、システム開発契約書の項目チェックや、契約書の作成などが可能です。システム開発の契約書作成の際には、ぜひ一度ご相談ください。
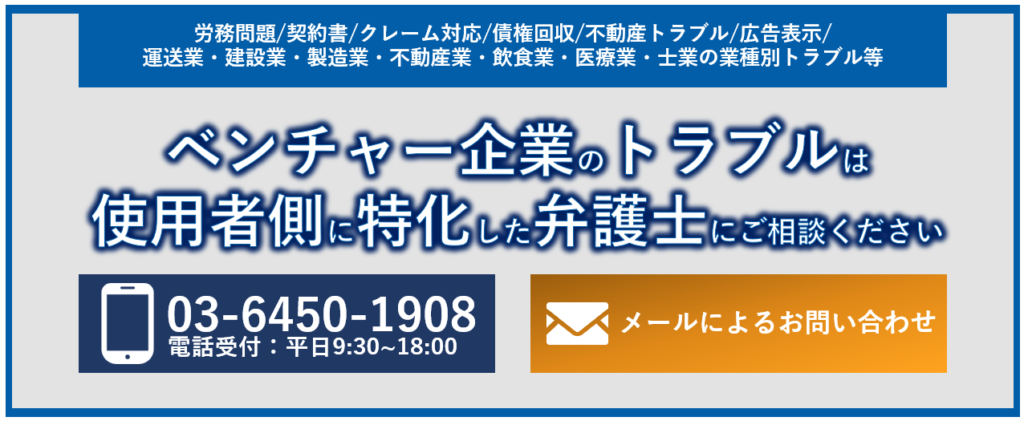

この記事の監修者
虎ノ門東京法律事務所 弁護士
中沢 信介
東京弁護士会所属。都内法律事務所パートナー弁護士を経て虎ノ門東京法律事務所参画。台東区法曹会副幹事長兼弁護士実務研究会の代表に就任しており、法律相談担当も務める。