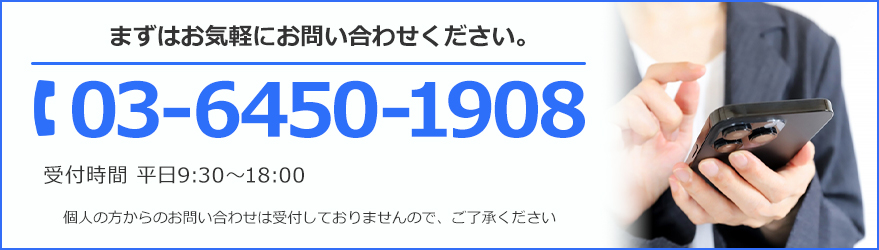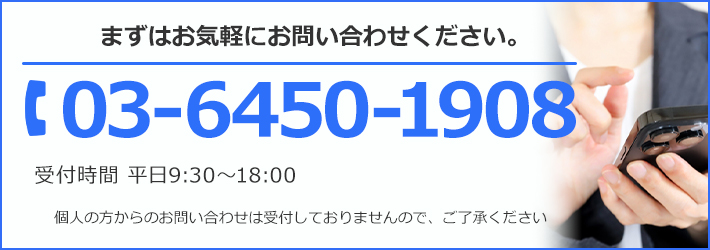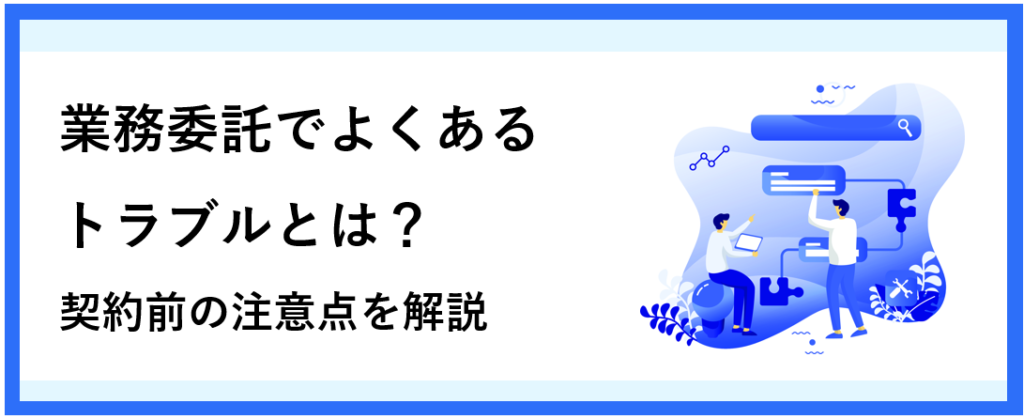
スタートアップや中小企業は、成長過程において業務が多忙となってきた場合に、いきなり人を雇用するのではなく、外注をすることが多いのではないでしょうか。この際の契約を業務委託契約といいます。ただ、この業務委託契約は少し厄介でしっかりと理解をしておかないと様々なトラブルが発生します。本記事では、業務委託契約の法的性質、メリットに触れつつトラブルについて、スタートアップ・中小企業に精通した弁護士が詳しく解説します。
業務委託契約とは
業務委託とは、自社の特定の業務を、自社の社員にやってもらうのではなく、外部の企業や個人に依頼する契約のことです。厳密には、民法上には「業務委託契約」という契約は定められておらず、「請負契約」(民法632条)、「委任契約」(民法643条)または「準委任契約」(民法656条)、また、これらの混合的な契約全般を指します。委託される側(受託者)は、委託する側(委託者)から受けた仕事の成果物・役務を提供することで報酬が支払われます。
業務委託を行うメリットには、人を雇用する場合にかかる固定の給与や社会保険料などのコストを削減できること、業務量の変動へ柔軟に対応できること、専門知識を要する業務を任せられることなどがあります。他方で、以下でご紹介するようなトラブルが起きる可能性もあります。業務委託を検討されている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
業務委託契約で起こりやすいトラブル
業務委託契約は、契約内容があいまいなまま業務が開始されていまい、後々トラブルとなることが多くあります。特に以下のようなトラブルが多いため、よく話し合って内容を取り決めることが必要です。
納期に関するトラブル
業務委託契約でよくあるトラブルの一つに、成果物の納期に関するものがあります。特に委託者側は注意したいところです。報酬を支払う覚悟の元、受託者に業務を依頼したのに、「納期に納品されない」「納期の認識がずれていた」「納品されないまま音信不通になった」などとなってはその後のスケジュールの調整なども含めて業務に支障が生じます。
一方で、委託者側の突然の仕様変更や納期指定の失念、途中で作業範囲を変更するなど、委託者側が納期に関するトラブルの原因とならないように注意することも必要です。
報酬の支払いに関するトラブル
報酬の支払に関するトラブルもよくあるトラブルです。報酬の支払内容・条件(成果物の品質の基準、報酬の発生するタイミングなど)について委託者・受託者の認識が違ったり、契約上不明瞭だったりすると、報酬支払の際にトラブルが発生する可能性があります。
また、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)や下請代金支払遅延等防止法(下請法、2026年1月からは製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)の対象になるような取引では、納品日から60日以内に代金を支払わなければならない(フリーランス新法第4条、下請法2条の2第1項)など、いくつかのルールを守らなければ、法令違反になってしまいます。
修正対応や保守管理に関するトラブル
制作に関する業務を委託した際は、成果物の修正や保守管理の対応について、トラブルになる可能性があります。例えば、受託者から、「納品後の修正は追加報酬が発生する」「納品後の保守管理について、高額な報酬が必要」と主張されるような場合です。
情報漏洩に関するトラブル
自社の情報を受託者に渡す以上、情報漏えいトラブルの発生も考えられます。受託者の悪意や過失で情報が漏えいした場合、委託者が損害賠償請求を受けたり競合他社にノウハウが流れたりと大きな損害が発生する場合もあります。
契約の中途解約に関するトラブル
委託先の立場では、受託者から突然契約を中途解約されるおそれがあります。委託先が経営破綻や倒産などで稼働できなくなったり、突然これ以上は対応できないと契約を解除されたりするような場合です。このような場合、依頼していた業務について、他の委託先を探したり自社で対応したりする必要がありますし、対応できない場合は自分自身が顧客に対して債務不履行になってしまう可能性があります。
反対に、委託者側の都合で依頼していた業務が突然不要になった場合などは、業務委託契約を解除して業務を停めてもらう必要があります。
どちらの場合でも、契約の解除とその後の処理について定めておかないと、報酬の支払や途中までの成果品の取扱をめぐってトラブルになる可能性が高いです。
トラブル回避のためのポイント
業務委託契約書の締結
上記のトラブルを回避するため、口頭やメールのやり取りのみで契約を済ませるのではなく、業務委託契約書を作成することが重要です。
業務委託契約は、民法上、書面がなくても成立します。しかし、口頭やメールのやり取りのみで契約を済ませてしまうと、各条件の合意があいまいになってしまい、後から「言った・言わない」の問題にもなります。結果上で列挙したトラブルになってしまいます。
しっかりと契約書の形にして業務委託契約を締結することで、トラブルを回避できる可能性が高まります。
なお、フリーランス新法や下請法の適用を受ける契約の場合は、フリーランス新法第3条や下請法第3条に定められた内容を記載した契約書が必要です。
納期・契約期間の明示
業務委託契約書の中でも、納期・契約期間を明示することは特に重要です。①どのような成果物をいつまでに提出するか、②それに対する報酬の内容は、業務委託契約の中心であり、委託者・受託者の認識をあわせて契約書に明記しておく必要があります。
また、制作に関する業務委託の場合は、納品後の修正や保守管理についても、対応可能な期間や保守管理に対する報酬などを含めて記載しておくと良いでしょう。
秘密保持契約の締結
受託者の悪意や過失による情報漏えいは、委託者側で防ぐことは困難です。しかし、秘密保持契約を締結したり、業務委託契約の中に秘密保持義務・守秘義務の条項を設けたりすることで、秘密情報の取扱方法や情報が漏えいしたときの措置(損害賠償等)について合意することができます。秘密保持契約の存在は、受託者にとって、秘密情報を注意して扱おうという動機にもなります。
契約書面のリーガルチェック
業務委託契約は、メリットもある反面、上述のようなトラブルが発生する可能性がある契約です。トラブルを防止するには、実現したい内容に沿って、適切な業務委託契約を締結することが重要です。弁護士に業務委託契約のリーガルチェックを依頼することで、適切な業務委託契約を締結することができます。
業務委託契約をご検討の方はぜひご相談ください
本記事では、業務委託契約でよるあるトラブルや注意点についてご紹介してきました。業務委託契約を締結する際は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
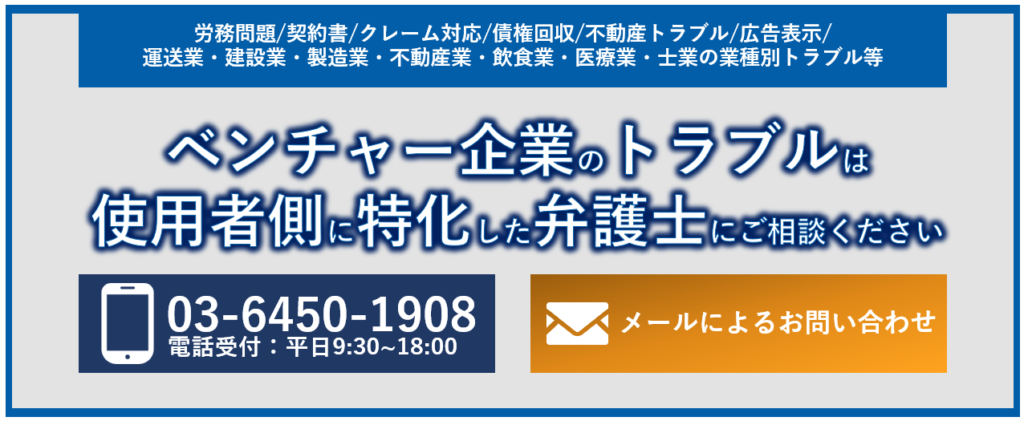

この記事の監修者
虎ノ門東京法律事務所 弁護士
中沢 信介
東京弁護士会所属。都内法律事務所パートナー弁護士を経て虎ノ門東京法律事務所参画。台東区法曹会副幹事長兼弁護士実務研究会の代表に就任しており、法律相談担当も務める。