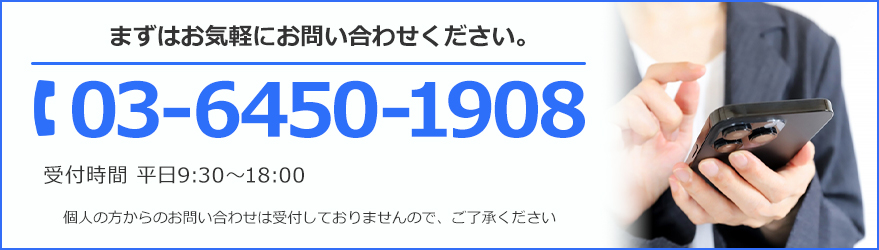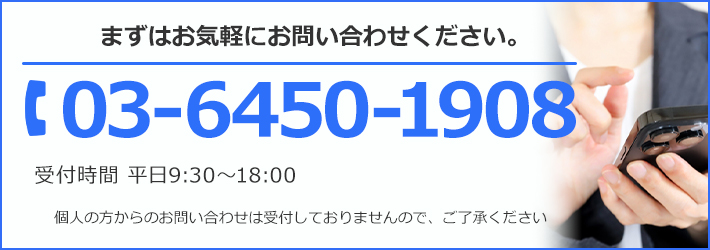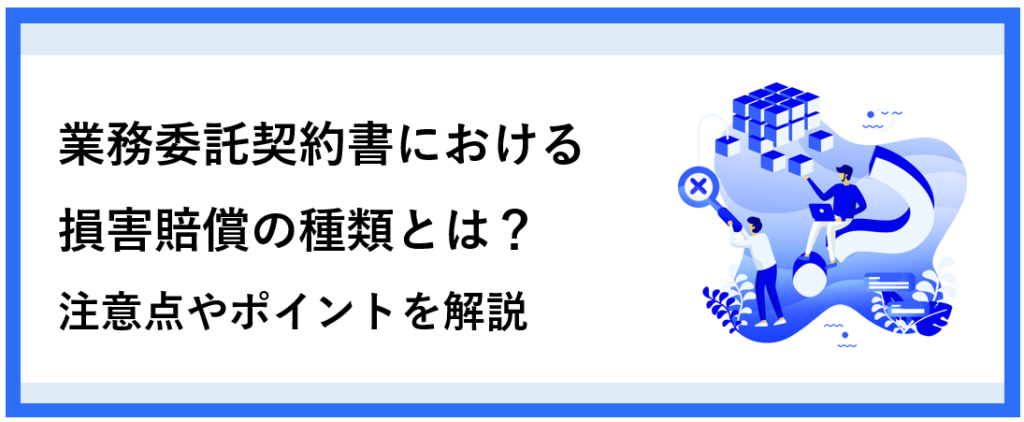
業務委託契約書における損害賠償条項は、契約違反やトラブル発生時に備える重要な規定です。しかし、責任範囲や賠償額の定め方を誤ると、思わぬリスクを抱えることになりかねません。本コラムでは、業務委託契約書における損害賠償の種類や基本的な考え方、実務で注意すべきポイントについて弁護士が解説します。
1.業務委託契約とは
業務委託契約とは、委託者が外注先(受託者)に対して業務を外注(委託)する場合に締結する契約書のことを指します。委託内容は様々ですが、、業務の外部委託に関する契約であるという点は共通しています。この契約の特徴は、委託者と受託者が互いに対等な立場で締結する点にあり、この点が、雇用契約と大きく異異なる点です。民法上は、「業務委託契約」という名称の契約は存在せず、13の典型契約の「請負契約」と「準委任契約」のいずれかに分類されることが一般的です。。
①請負契約とは
請負契約とは、仕事を請け負う請負人が依頼された仕事に対して、仕事を完成させたうえで、依頼者が仕事の完成に対して報酬を支払うという形態の契約を言います。この契約のポイントは、仕事の完成が目的であるという点です。仕事の完成に対して報酬を支払うという契約形式から、IT分野におけるシステム開発の委託等の場合によく使われます。
②準委任契約とは
請負契約が仕事の完成に対して報酬が発生するのに対し、準委任契約では仕事を進める作業自体に対して報酬を支払うという契約形態になります。そのため、準委任契約においては仕事・成果物を完成させる義務は基本的にありません。
よく聞く委任契約は、法律に関する業務を委任する場合のみに適用になります(弁護士に法律業務を委託する場合には委任契約となります。)。
2.損害賠償条項とは
契約関係にある当事者においては、契約書上で損害賠償の条項を定めておくのが一般的です。
損害賠償条項とは、委託者または受託者が契約内容に違反し相手に損害を与えた場合に、相手に損害賠償を請求することができるようにする条項です。この条項をもとに、もし契約不履行が起こった場合には損害賠償請求を行うことができます。万が一損害倍書条項が定められていない契約を締結していても民法に基づいた損害賠償請求は可能ですが、条項としてきちんと定めておくことによって、自分または相手方が、損害賠償義務を負担するとき、または被害を被ったときに、どのような点まで損害を賠償しなければいけないのか、どのような点まで賠償を求めることができるのかが明らかになります。
3.法律からわかる損害賠償責任
損害賠償に該当する行為はいくつかありますが、法律で規定されている内容は以下の3点に大別されます。
①債務不履行責任
債務不履行責任とは、民法415条第1項に規定されている内容であり、契約内容に違反したことに対する損害賠償責任を指します。
【民法第415条第1項】
| 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 |
上記に従うと
- 契約違反があること
- 契約違反をした側(債務者)に責められるべき理由や過失があること
- 契約違反が理由で損害が発生していること
- ①と②の間に因果関係があること
という条件を満たしていれば、債務不履行責任が認められるとされています。
②不法行為責任
不法行為責任の基本類型は民法第709条になります。
【民法第709条】
| 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
債務不履行責任と不法行為責任の発生要件は、契約関係がある当事者を前提とした場合には、(法律の解釈上、立証の観点からの違いはありますが、)大まかには同じとイメージいただけるとわかりやすいかと思います。
債務不履行責任と不法行為責任との間で一番違いが生じるのは、前者が契約関係が必要なのに対し、後者が契約関係がない当事者に対しても請求ができる点にあります。
(交通事故の被害者と加害者や、夫婦A(不倫された側)B(不倫した側)の不倫相手Cには契約関係がないですが、不法行為責任に基づき損害賠償ができます。)
③製造物責任(PL責任)
製造物責任は、製造物責任法に基づいた責任になります。この法律は、製造物の欠陥によって生命、身体またはほかの財産に被害があった場合に、被害者が製造業者に対して損害賠償を求めることができる、という法律です。主に製造物の作成に関する契約において適用されます(Aがメーカーで、Bが小売業者、Cが消費者の場合に、CがAの製品の欠陥を理由に損害賠償する場合が想定されます。(CとBには契約関係がありますが、CとAには契約関係がありません。)
PL法に基づいた損害賠償は
- 製造物に欠陥があったこと
- 拡大損害(製造物の欠陥によって生命、身体またはほかの財産に損害がでること)が発生したこと
- 製造物の欠陥によって損害が生じたこと
の3点を証明する必要があります。
4.損害賠償リスクを防ぐためのポイント
業務委託契約書において、損害賠償義務の範囲を明確にすることはリスクを管理する上(または請求できる範囲を明確にするために非常に重要です。
ここでポイントが一つあります。損害賠償条項において、損害賠償義務の範囲を定める必要があるのは、業務を受託する側の義務のみであるということです。
細かい議論は割愛しますが、業務を委託する側は基本的にお金を払うことがメインの義務になり、この金銭債務(=お金を払う義務)は履行できないということから、基本的に損害賠償となったときに負担するのは遅延損害金となるためです。
①受託側・委託側にとっての損害
そこで、それぞれにとって発生する可能性がある損害について解説します。
受託側の損害は、お金を支払ってもらえないことに対する遅延損害金が発生します。
他方で、委託側の損害は、利益損失や信用喪失など、受託者よりも損害の度合いが大きいものが想定されます。
②自社が業務を受託する場合の損害賠償義務範囲の限定のポイント
上記の通りですので、受託者側が債務不履行(契約の遂行ができない)となった場合の範囲を定めることは重要です。
受託者の債務不履行によって、委託者側は
・委託業務が遂行されなかったことが要因となる付随利益の損失
・委託業務が遂行されなかったことによる取引先等からの信頼の喪失
などの損害が想定されます。しかし、受託側としてこれらの損害をすべて賠償することは難しい場合もあります。そのため自社が受託側である場合には、契約書の項目で損害賠償義務の限定を行うことがポイントとなります。
システム開発契約の一般的な条文としては「損害賠償額は直近〇ヶ月以内に受領した委託料を上限とする」などの書き方がありますが、その他いろいろな方法によってリスクを回避すること(他方で委託者側では損害賠償を負担させること)が可能となります。
5.弁護士に相談するメリット
①書面のチェック・戦略的アドバイスをもらえる
弁護士にご相談いただければ、書面の形式や内容が正しいかという法的なアドバイスはもちろん、自社にとってのリスクを最小化するための戦略を含めた改善提案まで実施させていただきます。
②契約交渉の代理人請負を依頼できる
実際に契約する段階で、内容に同意してもらえなかった場合でも、契約締結に向けた契約交渉を、貴社の代理人として請け負うことができます。そのため、双方の企業の皆様にとって最適な契約締結にむけた交渉サポートも実施させていただきます。
③トラブルになっても安心
万が一、契約に関してトラブルが起こっても、契約締結の段階からご相談を頂けていれば、スムーズに解決に向けて動くことができます。そのため、トラブルの早期解決も可能です。
6.業務委託契約書の作成・チェックは弁護士までご相談ください
損害賠償トラブルは、起こってしまってからだと企業にとっても負担が大きく、解決までに時間もかかるトラブルです。そのため、事前に予防できる予防策をすべて実施したうえでの契約締結が何よりも大切です。
自社で実施する取引内容に関して、まずは専門家に相談のうえでの契約締結をおすすめしています。契約締結前にぜひ一度ご相談ください。
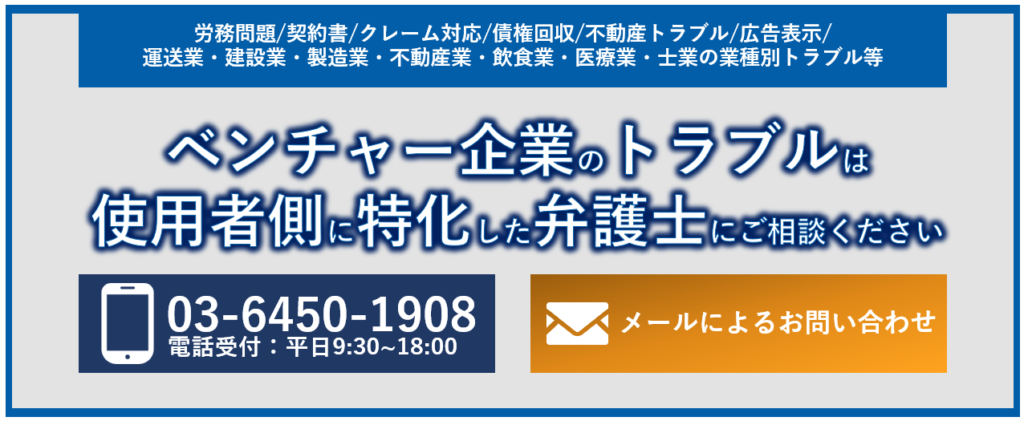

この記事の監修者
虎ノ門東京法律事務所 弁護士
中沢 信介
東京弁護士会所属。都内法律事務所パートナー弁護士を経て虎ノ門東京法律事務所参画。台東区法曹会副幹事長兼弁護士実務研究会の代表に就任しており、法律相談担当も務める。